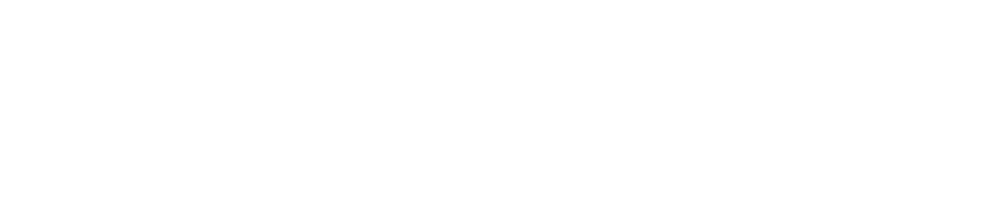3. 荒水の除去作業
Water Removal
お湯を使って生豆を洗った後、水滴を除去してから焙煎機に投入します。
これに関しても諸説ありますが、研究の結果、完全に濡れた状態で焙煎機に投入することはベストではない、と言える理由が多数あることがわかりました。
焙煎というものは、乾いた豆を煎ることが基本となりますが、先人たちが追求してきた焙煎の理論を生かす為にも、乾いた豆の焙煎に可能な限り近づけることが重要です。
速やかに「自由水」を除去し、「吸着水」だけの状態にする必要があります。キヨモコーヒーでは、除去する必要がある自由水を「荒水」と呼んでいます。
ここでは、荒水の除去作業の様子を公開しております。

■ 水切り
上記画像は、ざるで水を切った状態となります。(以下、多少の専門用語が入ります)
生豆が光っているのが解るかもしれませんが、この状態では、焙煎に入るには「自由水」の割合が高すぎますので、活性水分を一定にするために吸着水だけの状態にすることことにより、焙煎の安定度・再現性を高めます。
また、自由水を除去し、吸着(結合)水だけの状態にすることにより、焙煎時間の長時間化・えぐみを防ぐことができます。これはフレーバーの損失を防ぎ、乾いた豆と変わらないようなレシピで焙煎を行なうことが可能になります。
完全乾燥してからの焙煎のほうがレシピの再現性が高いですが、カビの再発生等のリスクが高まるため、洗った後は速やかに自由水のみを除去し、速やかに焙煎機に投入致します。
活性水分値や自由水分値を測定し、それに合わせてレシピの再現性を調整する方法もありますが、実際は湿度・部屋の温度・季節・炭火の状態等様々な要素にも左右されるため、再現性のために活性水分値を測定するという作業は行っておりません。
【補足情報】
研究の過程で、かつてキッチンペーパー等の紙類や、タオル等を使って水分を除去していたことがありました。
しかし、キッチンペーパーの紙の細かい繊維が付着することがあることや、タオルに付着している衣類洗剤等の付着を考慮し、現在では遠心力による水分の除去方法を採用しております。

■ 水切り後の生豆の様子。
こちらが、荒水を除去した状態の生豆です。先程の生豆の状態に比べ、表面の水分が光っておらず、自由水が除去されたことがわかるでしょうか。
この状態で再乾燥させると、カビや汚れの再付着の原因ともなるため、結合水のみが残った状態で速やかに焙煎機に投入することになります。
3.5.除去された荒水
Removed Rough Water
荒水の除去をした後に気になるのが、どれぐらいの自由水を除去できたか、というもの。生豆の表面や、隙間に詰まっていた自由水は、美しい豆の色を微かに纏い、透き通っております。
※下記の残留水の緑色の色素は、カフェインやクロロゲン酸等の水溶性のものが含まれますが、コーヒーの生豆は、洗っても水が豆自体に染み込みにくいため、
表面のみの酸の剥離となります。お湯洗いによる生豆表面のクロロゲン酸等の剥離は、お湯の温度調整により最低限に抑えられています。
剥離した分に関しても味に影響が出ない割合であることを確認しております(※0.1%未満の割合)

■ 水洗い後に除去した自由水
上記の写真は、約500gの生豆の水洗い後に遠心力で除去した自由水となります。
バシャバシャに濡れた状態で焙煎機に入れる方がいますが、機械的にも、焙煎過程としても良くない、と判断しております。
投入後、速やかに、長くても1分以内には生豆が乾いた状態になるように持っていくことが重要となるため、自由水は完全除去することが重要です。
キレイに洗った後の自由水であるため、上記の写真のように透き通った状態の自由水が採取できます。